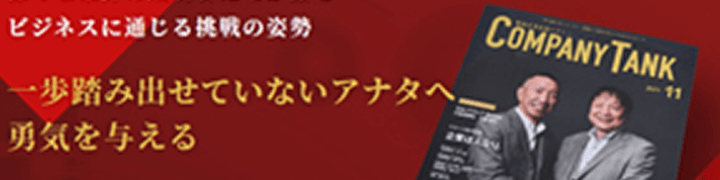巻頭企画天馬空を行く
「結果が出なければクビになる。そのくらいの
覚悟を持ってプロ契約をしたんです」
大学を経ずにVリーグ参戦を決断
 当時、バレーボール選手の多くは高校卒業後に大学へ進学し、そこから社会人チームへ入団するという流れが一般的だった。そんな中、越川氏はあえて大学には行かず、いきなりVリーグへ参戦するという決断をした。しかも、入団したのはVリーグ4連覇中の「サントリーサンバーズ」、またしても“勝利”を義務付けられた常勝チームだった。
当時、バレーボール選手の多くは高校卒業後に大学へ進学し、そこから社会人チームへ入団するという流れが一般的だった。そんな中、越川氏はあえて大学には行かず、いきなりVリーグへ参戦するという決断をした。しかも、入団したのはVリーグ4連覇中の「サントリーサンバーズ」、またしても“勝利”を義務付けられた常勝チームだった。
「高校で岡谷を選んだ頃から、バレーボール選手として上を目指してやっていくというのは自分の中で決めていました。それならば、日本代表、それもシニアAのチームに選ばれなければ意味がない。そう考えた時に、アンダー20で一緒にやっていたメンバーは皆大学へ行くし、同じ道を進んで同じ伸び方をしていては代表の座を勝ち取ることは難しいだろうと思い至って、もう一段上のレベルに身を置くことを決心したんです」
その覚悟通り、越川氏は入団1年目から試合に出場し、日本代表の合宿にも呼ばれながら、リーグ5連覇達成に貢献してみせた。しかし、同氏は現状に一切満足することなく、さらなる高みを目指して次の一歩を踏み出すこととなる。
「正直、『サントリーサンバーズ』での1年目は前年優勝のメンバーに支えられながら、“お客さん”のような感覚で優勝させてもらったと思っていますし、日本代表のほうも、アテネ五輪最終予選の最終選考メンバーまでは残りましたが、最終的にはメンバーから外れ、チームも五輪出場を逃しました。次の北京五輪では、何としてもメンバーに選ばれ、出場しなければならない――そんな状況下で私がした決断は、サンバーズとプロ契約を結ぶことでした。もともと、入団して3年くらいしたら海外でプレーしたいという気持ちも抱いていたのですが、ちょうど3年目のシーズンがリーグ準優勝で、このまま出ていくのもかっこ悪いよな、と思って。チームの中心選手としてしっかり優勝してから海外に挑戦しようと思い直し、チームの部長とGMに『プロ契約をしてください』と直談判したんです」
社会人スポーツでは、選手はチームを持っている会社の社員として所属しているため、一般の会社員と同じように給与が支払われる。引退後のセカンドキャリアについても支援してもらえる場合が多い。一方、プロ契約というのは、そうした社員としての枠組みをすべて取り払い、プレーの結果のみで評価される環境に身を置くことを意味する。安定した立場を捨てて、あえてプロ契約を結ぶという決断を下した越川氏は、当時どのような思いを抱いていたのだろうか。
「サントリーは、私のことを選手としても社員としても支えてくださって、本当に良い会社だなと感謝していました。ただ、自分がこの先もずっと選手として、あるいは引退後に社員として会社に残るイメージは持っていなかったんです。先ほど言ったように、入団当初からゆくゆくは海外へ挑戦したいと考えていましたし、それならばその思いをしっかり伝えて、プロ契約を結ぶのが筋だろうと思いました。また、ちょうどその年は自分が大学へ行っていれば4年生の年で、次の年からは同世代の選手がVリーグに入ってくるという状況でした。高校を卒業してすぐVリーグに進み、プロ契約を結んだという自分の選択が正しかったのかどうか、その結果を見る年でもあっただけに、この1年に懸ける思いは誰より強く、“もし結果が出なければクビだ”くらいの覚悟で臨んだんです」
それまで住んでいた社員寮を出て1人暮らしを始め、洗濯など自分のことは自分でやる代わりに、それまでチームの若手がしていた雑用なども「やりません」ときっぱり断りプレーに専念するようになった越川氏。チームとして初めてのプロ契約選手ということもあり、環境の変化になじむのに少し時間がかかったものの、プレーで結果を出し続ける同氏を見て、チームメートたちが徐々にサポートしてくれるようになったという。
「正直、今までやっていた雑用をやらなくなって、『生意気な若手だな』と思われたことはあったでしょうね(笑)。それでも、プレーでチームに貢献することが自分の契約なのだからと、そこはブレずに己の立場を貫きました。やがて、しっかり結果を出せるようになると、先輩のほうから『一緒に試合をしているんだから、その後のユニフォームはこっちで洗濯するよ』と言ってくださるようになって――そうしたサポートのおかげで私はプレーに専念できましたし、プロとしての覚悟を持って競技に臨んだことで、すべての物事が好転していったんです」
プロ契約1年目の結果は、チームとしてはリーグ優勝、個人でもMVPを受賞と、これ以上ない成績で終えることができた越川氏。その当時の心境を、率直に語ってもらった。
「自分の中で懸けていた1年だっただけに、とにかくホッとしましたね。ちょうど、翌年は北京五輪というタイミングでしたし、ここから先の自分の選手キャリアを考えた時に、大きな弾みになったことは間違いなかったと思います」
“プリンス”の称号を背負った北京五輪
2006~2008年の越川氏は、まさに男子日本バレーの象徴ともいえる存在となり、TV局が代々のエースに付ける“プリンス・オブ・ニッポンバレー”の称号も背負うこととなった。とりわけ、高い打点から相手のコートに突き刺さる高速ジャンプサーブは圧巻で、多くのファンを魅了していた。そんな同氏に、サーブにどのようなこだわりを持っているかについて尋ねてみた。
「もともと、私は肩が強くて強いサーブは打てたのですが、ミスが多く、決してサーブが得意な選手というわけではありませんでした。しかし高校2年時のある時、監督が指導者講習会でサーブのノウハウを学んでこられて、選手にフィードバックしてくださったんです。それを聞いた私は、自分なりの解釈をして試してみたところ、かなり安定して相手のコート内にサーブを打ち込めるようになりました。また、バレーボールにおけるサーブという動作は、他のレシーブ・トス・スパイクと異なり唯一、1人で練習することができます。そのことに気が付いた私は、自分だけのサーブをモノにしよう、得意なプレーはサーブだと言えるようにしようと思い、誰より練習に励むようになったんです。実際、まだ日本代表にそこまで定着できていなかった2004年のアテネ五輪予選あたりからは、他のプレーは負けてもサーブだけは負けたくない、サーブ1本打つために代表メンバーに入りたい、くらいの強い気持ちがあったことを覚えています」
そんなこだわりのサーブに加え、アタッカーとしても獅子奮迅の活躍を見せた越川氏。2008年には、男子日本代表を16年ぶりとなる五輪出場へ導き、北京の地で躍動した。しかし、大会中は5戦して全敗と、1次リーグで敗退し、世界との差を痛感することにもなったという。
「五輪の舞台に立ってみて体感できたのは、どの国も本気で勝つことを目指して大会に臨んでいるんだということでした。当たり前のことかもしれませんが、実際に相手と対戦してみて、あらためてそれを感じることができた。同時に、自分たちの現在地点を知ることもできて、世界と互角に戦っていくためには、チームとしても選手としても、もう1レベル上へいかないといけないなと思わされましたね」
ケガにもくじけず向かった海外リーグ
自分たちの現在地点を把握し、次へのステップへつなげるはずだった北京五輪――しかし、その試合中に越川氏をアクシデントが襲う。ジャンプ後の着地で膝をひねり、左膝の半月板を断裂。手術を要する大ケガを負ってしまったのだ。しかし、今後の選手生命が脅かされるようなケガだったにもかかわらず、越川氏はくじけることなく前を向き、翌年の2009年にイタリアの「パッラヴォーロ・パドヴァ」へ移籍し、かねて望んでいた海外挑戦を実現させた。
「自分の中で、競技を続けていく上での指標というか、中心に置くものが五輪でした。だから、次に五輪で勝つために、海外リーグを選択したんです。そこに関しては、ごちゃごちゃ迷わなかったというか、自分にとってはシンプルな決断でした。ただ、向こうのリーグへ行ってすぐに、また同じ左膝の半月板を負傷してしまって――その直後はさすがに不安な気持ちが大きかったと思います。チームとも、イタリアで手術するか、日本で手術するか協議があって、最終的には私のわがままを聞いて日本で手術をさせてくれました。そこから後は復帰に向けたケアを本当に丁寧にしてくれて、私自身も前向きな気持ちになれたんです。その間に、イタリアのスポーツ医療が非常に先進的であることも知れましたし、自分にとってリハビリ期間も大きな財産になりました」
日本とイタリア、2つのリーグを経験した越川氏。両国のバレーの特徴や違いについて、どのように考えているのか聞いてみた。
「イタリアの選手たちは個々の能力がものすごく高くて、また全員がプロ契約なのでとにかく死に物狂いでやっているという感じが伝わってきました。一方、細かい技術に目を向けると日本も引けを取らないなと思いましたね。また、選手だけではなく、サポーターの方々の応援の仕方も、日本とイタリアではまったく異なるんです。日本では好きな選手が所属しているチームを応援するのが主流ですが、イタリアは町を上げて地元のチームを応援します。その熱量はすさまじいものがありました」
海外3年目のシーズン、越川氏はチームの勝利のため、リベロという守備的なポジションを任された。いつもとは異なる役割を担う中で、同氏は新たな気付きを得たという。
「当時、チーム内にはドイツとイタリアのエース選手が私と同じポジションにいて、監督は私のプレーを信頼してくれていたものの、試合ではなかなか先発できない状況が続いていました。そんな中、リベロ1番手の選手が体調不良で、2番手の選手もケガで出られない試合があって、監督から『やってくれないか』と言われたんです。普段やらないポジションなので難しさはありましたが、チームのためになりたい一心で役割をまっとうしました。その時に、控えの選手がいるから勝てる試合もあるんだということに気が付いて、それからは例え先発でなくても、任された位置で役割を果たすことに誇りを持てるようになったんです」
巻頭企画 天馬空を行く
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ
- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子