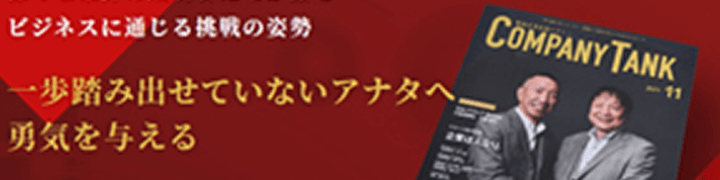巻頭企画天馬空を行く

野球評論家
福留 孝介
 1977年、鹿児島県出身。小学3年生からソフトボールを始め、6年生時には全国大会に出場。父に連れられて見学した中日ドラゴンズの春季キャンプで立浪和義氏と出会ったことを機にプロ野球選手を目指す。進学したPL学園高校で1年生時から活躍し、ドラフト会議では7球団の競合指名を受けるも日本生命に入社して社会人野球へ。3年後に逆指名制度で中日ドラゴンズに入団し、2002年の大幅なフォーム改造を経て球界を代表する強打者に成長する。2006年の第1回WBCでは、不調を乗り越えて準決勝でホームラン、決勝でタイムリーを放ち優勝に貢献。2008年から活躍の舞台をメジャーリーグに移し、2009年には第2回WBCで連覇を経験する。2013年に阪神タイガースに入団してNPB復帰を果たし、2017年には球団史上最年長の40歳でチームキャプテンに就任。2020年から古巣・ドラゴンズに復帰し、2022年9月に現役を引退した。現在は野球評論家として活躍しつつ、日本生命硬式野球部の特別コーチも務めている。
1977年、鹿児島県出身。小学3年生からソフトボールを始め、6年生時には全国大会に出場。父に連れられて見学した中日ドラゴンズの春季キャンプで立浪和義氏と出会ったことを機にプロ野球選手を目指す。進学したPL学園高校で1年生時から活躍し、ドラフト会議では7球団の競合指名を受けるも日本生命に入社して社会人野球へ。3年後に逆指名制度で中日ドラゴンズに入団し、2002年の大幅なフォーム改造を経て球界を代表する強打者に成長する。2006年の第1回WBCでは、不調を乗り越えて準決勝でホームラン、決勝でタイムリーを放ち優勝に貢献。2008年から活躍の舞台をメジャーリーグに移し、2009年には第2回WBCで連覇を経験する。2013年に阪神タイガースに入団してNPB復帰を果たし、2017年には球団史上最年長の40歳でチームキャプテンに就任。2020年から古巣・ドラゴンズに復帰し、2022年9月に現役を引退した。現在は野球評論家として活躍しつつ、日本生命硬式野球部の特別コーチも務めている。
野球人・福留孝介氏の半生は、決断の連続だった。プロ野球選手になると目標を定め、単身で大阪の高校へ進学。ドラフト会議では7球団の競合指名を受けながら、意中の球団に入団するために社会人野球の道へ。プロ入り後に何度も行った打撃フォーム改造、不調を跳ね返したWBC――己が進む道を自分で決めるのは、“1人でできる”という自信の表れでもあった。そんな同氏がメジャー挑戦とNPB復帰を経てたどり着いたのは、“助け合いで広がる可能性もある”という新境地。2022年に現役を引退した今、改めて自身の野球人生を振り返ってもらった。
思い描いた道を己の足で歩む
NPB(日本野球機構)で首位打者2回、リーグMVP1回、2度のWBC(ワールドベースボールクラシック)優勝。日米通算で2450本ものヒットを積み重ね、2022年に惜しまれながらも24年の現役生活に終止符を打った福留孝介氏。NPBでの通算打率は.286と、圧倒的な安定感と勝負強いバッティングで、日本を代表する強打者として長年にわたり球界をリードしてきた。同氏の野球人生の原点を探るべく、まずは幼少期について語ってもらった。
「私は鹿児島県の大崎町で生まれ育ち、父が町内会の集まりでソフトボールをしているところへ手伝いに行ったのがきっかけで、野球に興味を持つようになりました。ただ、片田舎だったので地元には少年野球チームがなく、小学3年生から学校の部活動でソフトボールを始めることにしたんです。当時から運動は得意なほうで、6年生の時には全国大会にも出場したのですが、そこでレベルの高い選手たちを初めて目の当たりにして、“全国にはこんなにすごい人たちがいるんだ”とショックを受けつつも、そういう人たちにも勝ちたいという強い気持ちを抱いたことを覚えています」
ソフトボールに打ち込みながら、福留氏は宮崎県で春季キャンプを行っているプロ野球チームの見学にも足を運んでいたという。そんな中、ある1人の選手との運命的な出会いが、同氏の歩む道に大きな影響を与えることとなる。
「中日ドラゴンズのキャンプを見学しに行った時、体格の良い選手たちの中で1人だけ、身長も体のサイズも大きくないけど、“ものすごく動くな”という選手がいて。それが、その年のドラフト1位で入団された立浪和義さん(現・中日ドラゴンズ監督)だったんです。体格的に恵まれていなくても、まったく見劣りすることなく活躍されているその姿を見て、自分も頑張ろうと思いましたし、自然と追いかける存在になっていましたね」
その言葉通り、福留氏は中学から軟式野球ではなく、プロと同じ硬式球で野球をするためにボーイズリーグに所属し、高校も立浪氏の母校であるPL学園高校を進学先に選んだ。地元の強豪校からも声が掛かる中で、大阪へ行くことを決めた背景には、さらに先を見据えた強い思いがあったという。
「立浪さんが出られた高校、というのももちろん大きかったですが、それだけではなく、本気でプロを目指すなら、大阪へ行って活躍したほうが、人の目に留まる回数も印象も違うだろうと思って、進学を決めたんです。その日のことは今でもよく覚えていますよ。深夜0時くらいに、両親の前で『ちょっと電話するね』と言ってPLの先生に電話をかけて、『お世話になります。今から両親に代わります』と話をして――その時まで両親は私がPLに行くことは知らなかったので、いわゆる実力行使でしたね(笑)」
かくして、地元を離れ大阪での寮生活を始めた福留氏。環境の変化や周囲のレベルの高さに戸惑いながらも、己の決めた道を一歩ずつ歩んでいった。
「全寮制の生活は、なかなかに大変でした。今までは母がやってくれていたことを全部自分でやらなければいけないし、それに加えて先輩方のお世話もしないといけない。練習でも先輩方のプレーを見て、こんな選手たちに自分は勝てるのだろうか、ずっとここで野球を続けられるのだろうかと何度も思ったのですが、自分の中で“プロになる”ということだけは心に決めていたので、そこへ向かって走り続けることができたんです」
7球団の競合も、社会人野球へ
高校1年生の秋から4番打者を任されるほどの活躍を見せた福留氏は、3年時には「高校No.1スラッガー」という評価でスカウトの注目を集め、ドラフト会議では同校の先輩・清原和博氏の6球団競合を上回る、高校生では史上初の7球団競合でドラフト1位指名を受けた。しかし、自らが希望していた中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツではなく、近鉄バファローズ(現・オリックス・バファローズ)が抽選で交渉権を獲得したため、入団を辞退して「日本生命」へ入社する道を選んだ同氏。その決断にも、やはり「自分で決めた道を行く」という強い思いが表れていた。
 「今となっては、自分のわがままだったなという思いもあるのですが、当時は私自身が幼い頃からよく見ていたドラゴンズとジャイアンツ以外の球団で、自分が野球をしている姿を想像できなかったんです。子供時代にキャンプを見に行って、こういうところで野球をやりたいとイメージを抱いていた球団に入りたい。その思いがあったので、悩むことはありませんでした。ドラフト会議を見ていた高校の校長室から親に電話して、『日本生命に行くよ』と。これについてはさまざまな意見があるでしょうが、“自分で決めれば後悔しない”というのが私の中で一番大きい決め手でした」
「今となっては、自分のわがままだったなという思いもあるのですが、当時は私自身が幼い頃からよく見ていたドラゴンズとジャイアンツ以外の球団で、自分が野球をしている姿を想像できなかったんです。子供時代にキャンプを見に行って、こういうところで野球をやりたいとイメージを抱いていた球団に入りたい。その思いがあったので、悩むことはありませんでした。ドラフト会議を見ていた高校の校長室から親に電話して、『日本生命に行くよ』と。これについてはさまざまな意見があるでしょうが、“自分で決めれば後悔しない”というのが私の中で一番大きい決め手でした」
日本生命に入社してからも、アトランタ五輪の代表メンバーに選出されて銀メダルを獲得し、さらに都市対抗野球大会でも優勝を経験するなど、着実にキャリアを積み上げていった福留氏。プロのペナントレースと異なり、“負けたら終わり”という環境でプレーし続けることで、1球にかける感覚の鋭さが磨かれていったという。
「社会人野球は、一試合の勝ち負けがすべての世界です。負けても次の日がある、とはならないからこそ、1つのボール、勝負所についての嗅覚は敏感になりましたし、それは私の野球人生でその後もずっと生かされていましたね。また、当時の日本生命には“ミスター社会人野球”として有名な杉浦正則さんが所属されていて、若い私のことを気に掛けてくださったんです。中でも記憶に残っているのが、『お前がプロに行くのは勝手だけど、“3年でどうせプロに行くから”という姿勢は絶対に見せるなよ。そういう態度では誰からも信頼してもらえないし、今は日本生命のチームの一員なんだから、そのために全力で必死にやるんだぞ』という言葉。自分にそのつもりがなくても、周囲からはそういう風に見えていたのかもしれないとハッとさせられて、その日から3年間、プロへ行くということはまったく意識せず、目の前の試合に集中するようになりました」
巻頭企画 天馬空を行く
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ
- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子