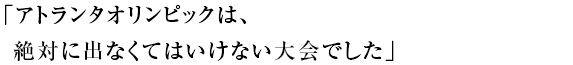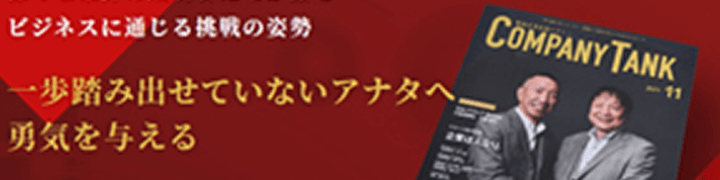巻頭企画天馬空を行く
![]()
![]()
バルセロナオリンピックからの4年間

1992年バルセロナオリンピックの女子マラソン日本代表に選出されると、2時間32分49秒のタイムでゴールし、銀メダルを獲得。日本女子陸上競技界において、64年ぶりとなるオリンピックメダリストの誕生となった。帰国後、一躍スポットライトを浴びるようになった有森さんであったが、次第に銀メダルを獲得したが故の苦悩を経験することになったという。
「バルセロナオリンピックで金メダルを取ったワレンティナ・エゴロワ選手と比べて、自分の技術にはさまざまな課題がありました。『自分はまだまだ弱い』。もっと強くなりたかったですから、そのためにモチベーションを高めていきました。
しかし、私のそういう思いや行動は空振りに終わってしまいます。というのも、自分の気持ちの盛り上がりに対して周りの受け止め方があまりに嚙み合わなかったのです。『メダルを獲るなんてすごい』と私を持ち上げる一方で、『調子に乗って、特別扱いを求めている』と、腫れ物を扱うような感じで接してくる人もいました。なぜそうなってしまったのか。当時の女子陸上競技界には、オリンピックメダリストといった世界で結果を残した経験を持つ人材がおらず、ノウハウがなかった。そのため64年ぶりにオリンピックメダリストが誕生したとき、その人をどう扱っていけばいいのか誰にもわからなかったのです。
あの時期は本当に苦しみました。自分の境遇を理解できる人が周りにいなかったので、相談もできません。実業団の中で自分の居場所がなくなり、どんどんいづらくなってしまう感じでした。『メダリストになったのがいけないのかな』と、思い詰めたこともありましたね」
周囲との軋轢に戸惑い、思い悩む日々を過ごす中、スランプに陥ってしまったという有森さん。そこから、どのようにして自らを奮い立たせていったのだろうか。
「やはり、自分の中で『この状況はおかしい』という思いは絶えずありました。そして、このまま泣き寝入りして選手生活を終えたくないとも思っていましてね。自分が抱いている疑問や考えを投げかけて、この環境を変えていくしかなかったのです。
だけど、メダリストは時間とともに世間の記憶から忘れ去られてしまう存在です。次のメダリストが出たら、その前のメダリストは当たり前に消えてしまう。すでにバルセロナオリンピックから2年が経ち、その間満足に走れていなかった私は、世の中から消えかかった存在でした。そんな私が声を挙げたところで、きっと誰も聞く耳を持ってくれません。何としても、もう一度こちらに周囲の目を向けてもらう必要がありました。そのためにも、誰もが認める実績が必要だったわけです。アマチュアのアスリートにとって最高の栄誉とは、すなわちオリンピックのメダルにほかなりません。話を聞いてもらうためには、再びオリンピックに出て、何色でもいいからメダルを獲るしかなかったのです。私にとってアトランタオリンピックは、出場したいではなく、出場しなくてはいけないものでした。
とはいえ、当然オリンピックへの道は険しかったです。スランプを克服するために厳しい練習を積み、悔しい思いをたくさん味わいました。その過程で踵を痛めてしまい、手術をすることになりましてね。そのときは、さすがに心が折れかかりました。でも、手術をした病院に入院していた人たちが、『次のオリンピックでも頑張ってね。応援しているよ』と、温かい言葉をかけてくださったのです。ここにいる方たちは、普段の生活を取り戻すために必死にリハビリ生活を送っている。それに比べて、走れるか、走れないかという私の抱えている悩みがすごく贅沢であることに気付くことができ、気持ちが軽くなったのです」
初めて自分で自分を褒めたあの日
見事に復活を果たした有森さんは、1996年アトランタオリンピックで銅メダルを獲得。ゴール後のインタビューで語った「自分で自分を褒めたい」は、同年の流行語大賞に選ばれた。
「自分の中でやり切った感はありました。バルセロナオリンピック以後、思うようにいかないことばかりで、苦しんできましたからね。正直、自分があのような状況でオリンピックを目指すということは、おそらく誰も想像できなかったでしょう。それがオリンピックに出場できただけなく、メダルを勝ち取れたということは、奇跡的だと自分でも思います。そういう4年間の出来事を、あのインタビューで一つひとつ振り返ったとき、すべてに納得して自分を受け入れることができました。素直に『自分はよくやった』と思えたのです。それで、あの言葉が出てきました。もしも、あの場面が周囲からブーイングを浴びせられるような状況だったとしても、私は自分のことを褒めたと思いますよ。
そして、もう一度メダリストの肩書を得ることができた私は、落ち着いて自分の感じている疑問や考えを組織に投げかけることができました。その中で、私の思いに共感してくださる人が少しずつ増えていき、一緒になって戦ってくださったのは心強かったですね」
巻頭企画 天馬空を行く
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ
- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子