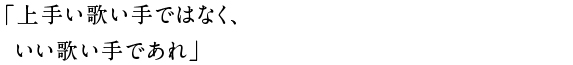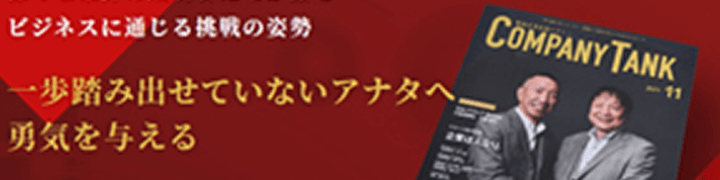巻頭企画天馬空を行く
![]()
スランプからの再起
デビュー曲「高校三年生」が大ヒットし、念願の流行歌手として成功を収めた舟木氏。その後も数々のヒット曲を飛ばし、大きな賞をいくつも受賞するなど、華々しい活躍を見せた。しかし1970年代に入ると、その勢いにも陰りが見え始める。時代の移り変わりとともに変化していく歌謡界において、成功を収めた自身の立ち位置を見失ってしまったのだという。
「実は、デビュー2〜3年目くらいから『この世界は、自分が思っていたのとはちょっと違うな』と思い始めていた。僕はそれまで芸能界を表からしか見ていなかったわけだけど、実際に業界に身を置けば自ずと裏側が見えてくるようになるし、そこに広がる堀の深さというものを実感したんだよね。芸能界に憧れていたからこそ、その落差も大きくて、自分の思い描いていた世界と実際とのギャップにだんだんついていけなくなった。そして『はたしてこの先、自分はこの稼業を続けていくことができるのだろうか』と悩んだ。まあ、それはこの世界に生きる人なら誰しもが一度は経験することだとは思うけどね。
結局僕は、10年目くらいで『ダメだ、こりゃ』となり、自分でテーブルをひっくり返してしまった。仕事に対して投げやりになってしまえば、相手もその様子を見て仕事を持ってきてくれなくなる。そしてますます腐ってしまう─そんな悪循環が始まったんだ。そんな日々を過ごしていて、40歳を過ぎた頃だったかな、ふと『まだまだ長いな、これから先の人生は』と改めて思うことがあったんだよ。そこで、自分の気持ちをもう一度整理しようと考えた。そして47歳、デビュー30周年のタイミングで、自分の同世代に向けて歌を歌っていこう、というスタンスを定めて仕切り直したんだ」
自分自身を見つめ直したことで、再起へのきっかけを掴むことができたという舟木さん。社会の変化の中で、どのように歌と向き合ってきたのか。
「僕は20代前半の若い時分から、1人の人間が何十年もコンスタントにヒット曲を出し続けていけるわけがないと思っていた。でも、ヒット曲がなくなったらお客さんがこなくなった、なんて単純な話だと困るわけで、やはり本人そのものが大きくなっていく必要があると考えていたんだよね。そうした中で最終的に行きついた境地は、上手い歌い手ではなく、いい歌い手であれ、ということだったんだ。
僕は1966年に出した「絶唱」という歌で、日本レコード大賞の歌唱賞を頂くことができた。それまでの受賞者を見れば、三橋美智也さん・越路吹雪さん・フランク永井さんなど、そりゃそうそうたる名前が並んでいるわけですよ。そんな賞を頂いたことで、『もうミスはできないな』という感覚が生まれてしまった。そうすると、芸事として外に向けなくてはいけない力が失敗をしないようにと内に向き、歌が小さくまとまるんです。芸能界の理想と現実を目の当たりにしての苦悩、そして歌い手としてのエゴのようなものが絡まりあって、僕は大スランプに陥ってしまったんだ。そして仕事がなくなった。
実際に仕事がなくなるかどうかはさておき、自分のしてきた経験は、プロと名のつく立場で仕事をしている人ならば誰しも味わうものではないかと思う。自分はプロの歌い手だけど、プロなら上手い歌を聴かせて当たり前。それを踏まえて、どうすればお客さんに喜んでもらえるかを考えなきゃいけない。そこでテクニックに走ると、本質を見失ってドツボにはまるわけです。特に自分の場合は若くしてヒットを出せたおかげで、デビュー当初から黙っていてもお客さんが集まってくれていたから、それが顕著だった。
ただ、実際に仕事が減ってきた中で落ち着いた時間を過ごせたことで、本来の自分の思いにもう一度立ち返ることができたのも事実なんです。『俺は上手い歌い手ではなく、いい歌い手になりたかったんじゃないのか』ってね。それで歌、そしてお客さんのことをそれまでよりも真剣に考えるようになったことが、今の自分につながっている最大の要因だと思います」
役者・舟木一夫として
 舟木さんは歌手として活躍する傍ら、1964年にはNHKの大河ドラマ「赤穂浪士」で役者としてのキャリアもスタートさせる。その後、1966年には大阪・新歌舞伎座で1ヶ月公演を行い、役者としての第一歩を踏み出した。今では1ヶ月公演の座長として確固たる地位を築いている舟木さんだが、役者への道は当初、望んでいたものではなかったそうだ。
舟木さんは歌手として活躍する傍ら、1964年にはNHKの大河ドラマ「赤穂浪士」で役者としてのキャリアもスタートさせる。その後、1966年には大阪・新歌舞伎座で1ヶ月公演を行い、役者としての第一歩を踏み出した。今では1ヶ月公演の座長として確固たる地位を築いている舟木さんだが、役者への道は当初、望んでいたものではなかったそうだ。
「『赤穂浪士』に出たそもそものきっかけは、脚本を書かれた村上元三先生のいたずら心。当時、詰襟を着て歌を歌っていた僕をテレビで見て、『かつらが乗りそうだから、出してみたらどうだ』と思われたことから話が来た。その後に新歌舞伎座の舞台を踏むんだけど、当時はそれがイレギュラーな仕事だと思っていたんだよね。『こういう仕事もやっていくのかな?』という程度の思い。ただ、その翌年にも明治座の舞台に立ち、その公演期間中に翌年のスケジュールも決まっていて、マネージャーに『これはレギュラーとして考えるべき仕事なのか?』と聞いたら、そうだと。そんな感じで僕の役者人生は始まったわけです。
とはいえ、仕事としてやる以上はきちんとしたものをお見せしないといけない。だけど、元々僕は流行歌手志望で演技のことなど考えもしていなかったから、全くと言っていいほど役者としての知識がなかった。だから、とにかく勉強しましたよ。まあ、元々時代劇は好きで、映画なんかもよく見ていたので、勉強していくうちにかつて見た作品の記憶がよみがえってきて、大変助けられましたけどね」
気が付けば始まっていた、舟木さんの役者人生。当所から、やりがいや面白さを見出せていたのだろうか。
「自分は出演する人たちの中で一番若いのに真ん中に立っているわけだから、面白いかどうかというよりも、とにかくやらなきゃいけなかった、という思いでしたね。最初はとにかく、普通に動けて普通にしゃべれるようになること。最初の5年くらいはその勉強をずっとしていたね。周りの諸先輩方には、分からないことを片っ端から聞いて回っていた。
役者に関して言えば、時代劇の役者は大別して、“義経型”と、“弁慶型”の2つに分類される。 自分に要求されるのは“義経型”だろうという自覚はあったので、たまたまご縁ができた長谷川一夫さん、大川橋蔵さんといった大先輩の演技をよく見て、盗めるところは少しでも盗もうとしていたよ」
「技術は見て盗め」という言葉は、役者ならずとも技術を要求する世界ではよく言われるものだ。その大切さについて、舟木さんは熱を込めて語る。
「僕らの若い頃は、先輩が芝居をしている時には必ず舞台袖に行って、じっと見ていたものだった。こと芝居に関して言えば、教わるのではなく盗んだものでないと身にならないと思っている。だからとにかく、何でも盗もうとしていたよ。
もちろん、その中には不必要なものもたくさんあった。でもそれは、盗んでみないと気がつけないものなんだ。何が使えて何が使えないのかは、自分の手元においてみた時に初めて分かる。だから無駄だと思えるようなものもずいぶん盗んだけど、それが後に役に立つこともあったよ。
例えば、自分は幸いにして若い頃から真ん中、つまり主役を任されることが多かったから、斬り方を勉強する必要はあっても、斬られ方を勉強する必要はなかった。でも、実際に役を演じる際には、周りには斬られるプロが揃っているわけだから、僕自身も斬られ方を斬りながら勉強する。すると、役によって斬られる側に回った時に活きる。そういうことも経験だよね」
また、舟木さんは演技者の“血”についても言及した。
「自分は、典型的な“野育ち”なんですよ。一方で役者の世界には父から子へ、という“血”の存在がある。先祖代々受け継がれてきた演技のDNAによって生まれるものもあるし、一方で自分のような存在も絶対に必要。その2つが合わさることで、いい芝居が生まれていくんだと思うんだ。一方で流行歌の世界は、継承できるものではないのだけれどね」

巻頭企画 天馬空を行く
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ
- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子