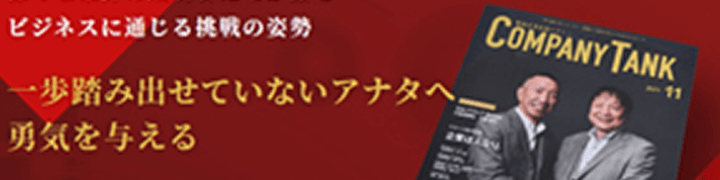巻頭企画天馬空を行く
![]()
「思想」を乗せるものづくり
愛媛県で生まれ、15歳の時に大阪で靴下問屋の丁稚となった越智会長は、「お客様は天皇陛下より偉い」と聞かされ仰天したという。誰もが天皇陛下を崇拝していた時代を知ればこそだ。しかしその教えに一切の疑いを挟まず、常に「お客様のために」尽くしてきたからこそ、越智会長の、そしてタビオの今がある。お客様を欺くなどもってのほかだ。
実は今の価格重視の様相は、会長が起業を果たした1968年頃とよく似ているという。それまで国内工場に生産を委託していた大手商社が、人件費の安い韓国に生産拠点を移した。だが会長に言わせると、出来上がってきた製品はまさに「安かろう悪かろう」。やがて韓国での人件費が高騰すると、今度は生産拠点を台湾に移し、国内の生産者を苦しめることとなった。高度成長期に伴い生産者も一度は息を吹き返したが、バブル崩壊を機に中国へと生産拠点が移り、現在はインドネシア、タイ、ベトナムなどに移行しつつある。国内の生産者はどんどん衰退し、消費者は安いがそれなりの商品を手に入れることが当たり前となってしまったのだ。
「技術力なんてそんな大それたものやありゃしまへん。私の仕事は良い靴下を作ることだけですから。
商品は、思想が形になったものなんですよ。音楽家の思想が形になったものが楽譜であり、画家の思想が形になったものが絵画となる。そして靴下職人の思想を形にしたものが靴下であり、思想のない者に、きちんとした靴下は作れません」
会長による一貫したものづくりへの想いは、消費者への何よりの配慮なのかもしれない。
履いて確かめたいから「履かない」
越智会長は普段、靴下を履かない。噂には耳にしていたが、本当なのだろうか。
「ああ、ほんまでっせ。どうぞ、こっちに来て見とくんなはれ」
素足にサンダル。公の場に姿を現すとき以外、会長は冬でもこのスタイルを貫いている。新商品が企画されると、それが婦人物であっても商品化する前に会長が自ら試し履きをする。試し履きをする前に別の靴下を履いていると皮膚の感触が鈍り、新しい靴下の履き心地を感じられなくなるのだそうだ。消費者が靴下に足を通した瞬間の感触を想像しながらの靴下作りを大切にしている会長の身体には、履いた瞬間の心地良い感触が記憶としてしっかりと刻み込まれているという。無論、会長のGOサインが出なければその靴下が市場に出回ることはない。
サンプルとなる靴下を、会長は一気に、突き抜くように履く。その際、表糸と裏糸のバランスが悪くて上手く滑らず足にひっかかったり、つま先やかかとの縫合部分であるゴアラインが上がったり下がったりするようなら即刻ボツ商品だ。
 「靴下は第二の皮膚なのです。皮膚と靴下の中に入り込んだ米粒が、外から誰が見ても米粒だと分かるような薄さやフィット感。ゆるくもなくきつくもなく、肌をそっと優しく包み込む履き心地。履いていることをつい忘れるような靴下が理想です。そこまで追求したら、海外では作れない」
「靴下は第二の皮膚なのです。皮膚と靴下の中に入り込んだ米粒が、外から誰が見ても米粒だと分かるような薄さやフィット感。ゆるくもなくきつくもなく、肌をそっと優しく包み込む履き心地。履いていることをつい忘れるような靴下が理想です。そこまで追求したら、海外では作れない」
タビオの品質を支えているのは、1992年に「靴下屋共栄会」という名で設立された協同組合(現・タビオ奈良 株式会社)だ。靴下の町、奈良・広陵町にあって靴下の生産を担う工場数社と同社で設立した。会長曰く、「世界一の技術を持った職人がここに揃っている。仮に共栄会が持つ生産設備全てを海外に移設しても、同じ靴下は作れないだろう」。
機械の使い方がマスターできないとか、安定した電源供給がなされないとか、そういった環境面の話ではない。機械には固有の特性があって、それを調整する「感覚」が大切になる。
「『微妙に調整してくれ』と言って、それが理解できるのは日本人しかいません。一度調整するのでも、1mm調整するのでもない。微妙な調整が“絶妙”なさじ加減になるんです」
海外に行ったら、微妙という言葉は通用しない。あえて調整する「技術」と言わなかったのは、まさに感覚に頼るところが大きく、日本人はその感覚に長けているためだ。
一生一事一貫で道を究める
タビオの売上のおよそ8割は婦人靴下だ。では男性は靴下に興味がないのかと言えば、無論そのようなことはない。男性でもたいてい10足くらいの靴下は持っているものだろう。
しかし、その10足を全て順番に均等に履いているだろうか。気に入った2〜3足を交互に履いてはいないだろうか。
「せっかくお客様に買って頂いても、履いてもらえなかったら靴下職人としてのプライドはズタズタです。靴下は履いてもらってなんぼのもの。もし履いてもらえないのであれば、その理由を聞きに行き、納得できる回答が得られなければ返してもらいたいくらいですわ(笑)。でも、そんだけのプライドを持った靴下職人が、今はほとんどおらん」
履かれない靴下は「屑下(クズした)」だと会長は言う。クズならゴミとして処分されるが、箪笥の中の屑下は処分もされず、かといって使われもせず、箪笥の肥やしという不遇の生涯を送ることになる。
「そんな屑下を作らないためには、“誠”を持って作らなあきまへん」
会長は、今の社会には誠を持って商売に携わる人が少なくなったと感じている。商品を「価値」で売らずに「価格」で売るのは誠がない・・・と。またそのような商売人は、商いの道を究めず「術」で売ろうとする。だが、術の効果は一時的なものでしかない。術で儲けた会社もまた一時的であり、いつかは滅びるというのが会長の持論だ。
「剣術は剣道になった。柔術も柔道となり、商いの術は“商道”となっている。今も昔も、道を究めなければいつかは滅びるのです」
さしずめ、越智会長の場合は「靴下道」とでも言おうか。
会長の性格は豪放磊落だが、酒は飲まないし、ゴルフや麻雀もしない。またこれまで、靴下以外のビジネスを勧められたことも幾度となくあったが、いずれも手を広げなかった。一心に靴下道を究めてきたのだ。
「私のように学がない者が成功するための条件は、ただ1つ。それは“一生一事一貫”することです」
一生一事一貫─生涯、脇目も振らず1つのことだけに一貫して携わっていれば、いつか花開くという意味だ。
今の世の中を見れば、まるで多角展開する企業こそが優良企業のように認識されている。例えば、電機メーカーの純損益が本業よりもそれ以外のウェイトが大きいことはまさに、この状態を如実に象徴していると言えるだろう。しかし本来経営者は、1つの事業では心許ないから多業種に着手しようと考えるのであり、その時点で本業を究めようという気が薄れているのではないか。流行を求めて、利益率の高い分野に安易に進出してはいまいか。新たな事業に「誠」はあるのか・・・。
「満月を求めて崖っぷちを彷徨う経営者がいかに多いことか。マスコミや世相に踊らされて足元を見失い、崖から転落する経営者は実に気の毒だ。満月も満つれば欠ける。潮も満つれば引く。その道理が分かっていれば、決して転落することはないはずなのに」。
巻頭企画 天馬空を行く
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ
- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子