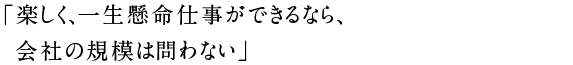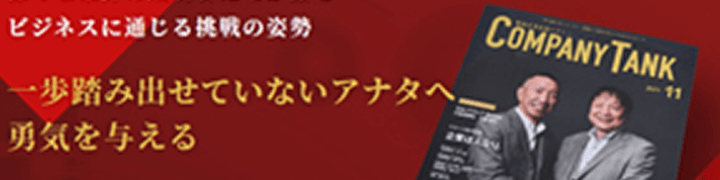巻頭企画天馬空を行く
![]()
時代の趨勢を追い風に
エージェントとして躍進
 1980年代はフォトエージェンシーが伸びた時代である。バブル景気で引き合いも多く、ライセンス料の単価も高かった。また、今日のようなインターネットはなく、パンフレットや書籍・雑誌・新聞など紙媒体によるマスメディアが情報の中心だったため、重版されればされるほどライセンス料が入った。
1980年代はフォトエージェンシーが伸びた時代である。バブル景気で引き合いも多く、ライセンス料の単価も高かった。また、今日のようなインターネットはなく、パンフレットや書籍・雑誌・新聞など紙媒体によるマスメディアが情報の中心だったため、重版されればされるほどライセンス料が入った。
だが、一方でアフロの売上はさほど伸びなかった。要因は、青木自身に「会社を大きくしよう」という気持ちがなかったことにある。当時も今も青木はプレイングマネージャーだが、80年代は1年のほとんどを海外での撮影に費やしており、経営はほぼノータッチ。「借り手が見つかったら請求書を送っておいて」と事務スタッフに指示するのが経営者としての主な仕事だった。
10周年を迎えても、社員は10名。だが「楽しく、一生懸命仕事ができるなら、会社の規模は問わない」と青木。楽しくない仕事を無理にするくらいなら、会社を大きくする必要はないというのが彼の持論だ。
ただし、自分が「楽しい」「やりたい」と思ったことは絶対に行う。例えば1992年、単価が低くて利幅の小さい報道系の写真部門をあえて創設した。これは世界規模でスポーツ写真を集めていたイギリスのスポーツ専門フォトエージェンシー「オールスポーツ」と提携したことがきっかけとなっている。
「最初はね、全く相手にされなかったんですよ。でも、1991年の世界陸上選手権の際に、ボスが会社に来てくれた。それでアフロが、小さいけれども楽しい会社であることを説明すると興味を持ってくれてね。だから私は彼に言い切ったんです。1年で、オールスポーツを日本でメジャーにする。だから日本でのオフィシャルエージェントにしてほしいと」
青木の熱意に感銘を受けたオールスポーツ社のボスは、1年目、ノーギャランティで契約。2年目はギャランティの最低保証額を求められたが、アフロはその3倍の額を販売した。3年目、最低保証額はなくなった。
一方で1991年にバブルが崩壊し、その影響が深刻になった数年後、多くのフォトエージェンシーの売上が下降線を辿り始めた。スポンサーの倒産が相次ぎ、かろうじて生き残った企業も広告費用を大幅に削減。イメージフォトも数を減らし、味気ないパンフレットやコマーシャルが増え始めた。
ところがそのなかで、アフロは売上を伸ばしていく。青木は当時、様々なメディアで取材を受けている。テーマはたいてい「不景気の中で成長している要因は?」だ。
「経営戦略なんて難しいことを考えていたわけではありません。取材には、楽しく働いていることが功を奏しているんですかね、なんて答えていたんです。インタビュアも困ったでしょう(笑)」
それでも青木の話から分かる、明らかな成功要因がいくつかある。
1つには、他のエージェントを追随しなかったこと。不況にあえぐフォトエージェンシーではこの時期、リストラを敢行した。採算が合わないから人件費を減らすというのは今も昔も変わらない常套手段だが、当然起こりうるのは「サービスの低下」だ。一方、アフロでは逆に社員を増やした。今のようなデジタルフォトストックのない時代、顧客側としてはライトボックスで欲しい写真を選ぶしかなかったが、アフロでは「このようなイメージの写真が欲しい」という顧客のニーズを受けてスタッフが当たりを付け、自社になければ世界中に手配した。社員数を減らしたフォトエージェンシーではそこまで手が回らない。どちらの顧客満足度が高いかは明らかだ。
2つ目はアフロが世界のスポーツに特化していたことだ。それまで世界で起こったスポーツイベントの写真と言えば、スポーツ専門誌かスポーツ新聞などにニーズが限られていた。しかし90年代、Jリーグ創設を機に、選手たちの目標は「日本のトップ」ではなく「世界のトップ」となっていく。観客の目も必然的に世界に向き、それに応じてスポーツ写真のニーズが高まっていったのだ。
そして1998年。長野オリンピックのオフィシャルエージェントに選ばれたことでアフロは地位を不動のものにした。
「1976年にオーストリアのインスブルックで開かれたオリンピックでは、プレスカードすら発行してもらえなかった。300mmの望遠レンズもない時代、一般の観客席から狙って1枚もまともな写真が撮れなかったことを覚えています。そんな悔しい思いをしてから8年後、サラエボで初めてプレスカードが手にできた。さらに10余年、長野でオフィシャルエージェントになれた時は、夢が実現したと思いました」
実績のなかったアフロがエージェントとして認められたのは、写真に溢れる躍動感。「単なる報道写真ではなく、作品として写真に残す」という青木の熱意が選考委員の心に届いた。
巻頭企画 天馬空を行く