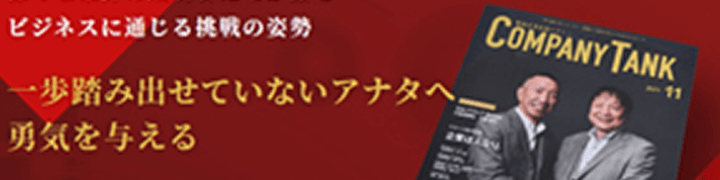巻頭企画天馬空を行く
![]()
サイクルベースあさひ 大型店誕生の裏側
「お客さまの消費者利益を守れないという思いもありましたし、このままではいけない」と痛切に感じたという。そして一念発起し、プロショップを社員に託して、下田と若い社員の2人で大阪・寝屋川に新しい自転車店を誕生させた。下田42歳の1989年、「サイクルベース あさひ」初の大型店舗の誕生である。
「プロショップをやっていた経験を活かして、自転車の安全性やメンテナンスの重要性、たくさんの自転車のなかから選ぶ楽しみ、乗る楽しみを、幅広い層のお客さまに提供できるお店を試してみたかったんです」
当時の自転車店としては破格に広い100坪あまりの店舗スペースに、マウンテンバイクからロードレーサー、スポーツ車、一般車、子ども用まで、ありとあらゆる層に受け入れられる商品を揃えた。下田自身が店に立ち接客し、メンテナンスにも加わった。これがまさに(株)あさひの現在の店舗スタイルの原型。当時としては画期的なスタイルで、下田は自分の理想にとことんこだわった。自身の手応えも大きく、顧客からの支持も初年度から圧倒的に高かった。

「『こんな自転車屋がほしかった』と言ってもらえたときは、やはり誰もが同じように感じてたんだと。売ったら終わりという店ではなく、最後まで面倒を見てくれる安全性が欲しかったのと、さまざまな選択肢のある大きな店舗で買うことの安心感を消費者は求めていたんですね。それまでは売る側も零細店が多かったし、店も小さいから品揃えも安さも追求できなかった」
このように、サイクルベース あさひは消費者の潜在的な願望の掘り起こしに成功していった。そして20年あまりを経た今、資本金20億6135万円、従業員数869名(共に2011年11月20日現在)、年間130万台もの自転車を販売する大きなチェーン店へと発展していった。名実ともに自転車専門小売業ではトップのリーディングカンパニーとなったのである。
「われわれの店舗は、自転車のサポート基地と捉えています。自分自身としては長年かけてプロショップで積んできた経験と自信がありましたので、ある程度の店舗数と販売実績に到達した時点で、自転車そのものを自分たちで作ることも開始しました。製造〜物流〜販売の一貫体制をとることによって、品質やデザイン、サービスの質を向上させ、価格も安くして、お客さまにもっと満足して頂くことに心を砕いてきました」
PB商品の開発 ネット通販への参入
1996年からプライベートブランドの開発に着手。現在、PBブランド商品の売上構成に占める割合は半数を超え、ホームセンターなどにも商品の供給を開始している。商品開発では、自転車のみならず幼児用ヘルメット、カギ、ベル、サドルなどのアクセサリー類、また他企業とコラボレートしたロゴ、キャラクターを使用した新ブランドも。増加するPBブランド商品に対応するため、2005年には三重県伊賀市に自社物流センターを取得し、9千坪におよぶ敷地に自転車8万台、パーツ約50万個の保管を可能にさせた。また2011年には、東日本地域に向けての配送拠点となる1万坪の物流センターを埼玉県久喜市に竣工。

実店舗での自転車販売を大切にしつつ、早くからインターネット販売に積極的に参入したのも、下田の優れた先見性を物語っている。
「インターネット販売は早い時点で開始しました。日本にネット市場が立ち上がったのが1996年。その翌年には当社もネット販売をスタートさせ、リアルとバーチャルの棲み分けを図ってきました。リアルの実店舗には一般の自転車初心者のお客さまにも来店して頂くことをコンセプトとしたのに対し、バーチャルのネット通販では全国各地のサイクルスポーツのコアなファンや競技者など、自転車のプロに購入して頂けるように意識したのです」
同社Webサイトには、約2万アイテムもの商品写真が掲載されている。結果、ネット通販の売上高でも自転車関連部門において圧倒的なナンバーワンを誇り、未だ右肩上がりの成長を続けている。
どのように心がけたら下田のような商才を発揮できるのかと尋ねてみたら、こんな答えが返ってきた。
「やっぱりお客さまをよく観察するようにしてましたね。突飛なことを考えるのではなく、どうやったらお客さまに来て頂けるか、買って頂けるかという商売の原点に一点集中する。われわれの極意は、他の誰よりもお客さまに気に入ってもらえる商品やサービスを提供するのみの一点です。と言っても、お客さまのニーズや課題は多種多様です。価格、品揃え、サービス、お店の大きさ、スタッフの愛想がいいか、クリンネスが行き届いているかどうかなど、100も200も課題があるわけです。僕は、その課題を一つひとつ乗り越え、一生かけてクリアしていくことが仕事なのだと考えています。それは会社が大きくなっても同じこと。私はずっと普通の商売をしている感覚なので、日々の地道な積み重ねが一番大切。仕事とはそういうものだと考えています」
巻頭企画 天馬空を行く