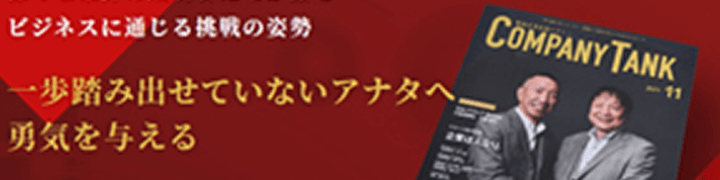コラム
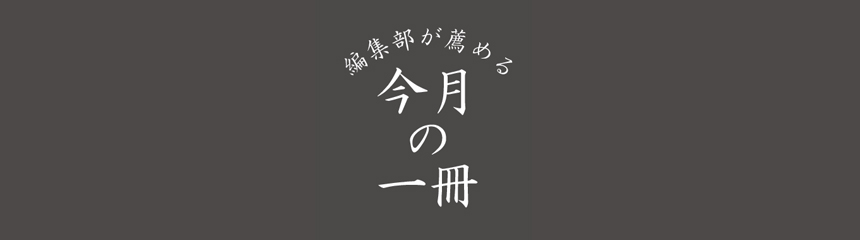
 本音が言えない環境が生産性を低下させ、
本音が言えない環境が生産性を低下させ、
コミュニケーション不全が組織をむしばむ!
その原因と対策とは?
「心理的安全性」とは、組織行動学の研究者エイミー・エドモンドソンによって1999年に提唱された概念です。これが高い組織は、誰に対しても安心して発言できる状態であると言われています。自由闊達な意見交換はメンバー間の情報共有をスムーズにし、業務への責任感の醸成にもつながり、組織全体に好影響をもたらします。反対に強権的なリーダーシップや風通しの悪い組織体制下では、個人のストレスを増大させるだけでなく、離職率の上昇や生産性の低下といった形で組織全体にも悪影響を及ぼします。こうしたコミュニケーションのずれを解消し、良好な人間関係を構築するために本書の著者が導入したのが、エマジェネティックス(EG)です。これは、アメリカで開発された脳神経科学と統計学に基づくプロファイリングツールで、100の質問への回答から脳の個性を分析し、行動や思考の特性を数値化します。本書では、心理的安全性の低下がもたらすデメリットや、それを高めることの重要性を解説。また「EG」の活用例を通して、多様な背景を持つ社員が協力し合える職場づくりの方法を具体的に記しています。組織構築や人材マネジメントを担う企業経営層にとって必読の1冊です。
《著者Q&A》
■この本を出版しようと思われた理由・動機を教えてください
私が経営しているNSKKグループでは、「心理的安全経営」の実現を目標に掲げているのですが、多くの経営者の方々から、心理的安全性を高めたいがうまくいかないというご相談をいただきます。実は、社員一人ひとりの個性を科学的に明らかにし、社員同士の相互理解を深めることができれば、簡単に実現できるにもかかわらず、日本ではそうしたツールの必要性を認知されている方が極めて少なく、努力が無駄になっている事例で溢れています。こうしたツールを使う必要性を世の中に知っていただければ、日本企業を元気にし、社会を活性化させ、失われた30年を取り戻すことにつながると考えたことがきっかけです。
■社会学者の宮台真司氏が言うように、心理的安全性が高まることで、帰属意識および挑戦心が育まれると思われますか?
はい。組織の心理的安全性が高まれば組織に対する帰属意識が高まり、失敗を恐れず挑戦しようというマインドになることは間違いないと思います。対人関係に対するリスクを負うことにためらいがなくなり、「失敗は学習のための糧となる」ということが、組織内で共有できるからです。
■中小企業と大企業では心理的安全性を高めるやり方は異なりますか?
基本的には変わらないと思っています。心理的安全性を損なうのは「『自分らしくあること』をこの組織では許されていない」と感じているからです。どんな組織でも、メンバーの一人ひとりが、お互いのことを理解し尊敬し合い、違いを尊重し、お互いの「あるがまま」を受け入れなければ、心理的安全はつくれません。やらなくてはならないことは規模に関係ないと思っています。
■チームにとって同質性と多様性のどちらがより重要だとお考えですか?
同質性が組織の強さを生んでいた時代もあったと思います。しかし、VUCAの時代(移り変わりが激しい時代)と言われる昨今では、同質性はもろさ、弱さを引き寄せてしまう可能性が高いと思っています。私自身は圧倒的に多様性が重要だと考えています。
■本誌の読者宛にメッセージをお願いします
組織を強くするにはまずメンバーの個性を客観的に知る必要があります。ところが日本人の多くは、目や肌の色、話す言葉や食べものなどが似ているからか、個性よりも集団の論理を押しつけようとする傾向があるかもしれません。しかし日本人も多様ですし、その多様性を活用することで組織を強くしてくれます。個性を科学的に知ることの有用性を知っていただき、本書を通してエマジェネティックスをご活用いただければ幸いです。
 賀川 正宣(かがわ まさのり) 賀川 正宣(かがわ まさのり)(株)EGIJ代表取締役、(株)NSKKホールディングス代表取締役。1968年生まれ。2008年にエマジェネティックス(EG)と出合い、自らの会社の経営にEGを取り入れて組織力と接客サービスの向上を体感し、大きく業績を伸ばす。グループ企業においては社員、アルバイト全員がEG研修を受講。2010年には携帯電話販売台数で日本一になるなど、目覚ましい業績向上を実現。2012年には持ち株会社に移行。他業種へと事業領域を拡大。全グループ企業でEGを活用し、成果を出し続けている。 発行:幻冬舎メディアコンサルティング URL https://www.gentosha-mc.com/ 発売:幻冬舎 URL https://www.gentosha.co.jp/ |