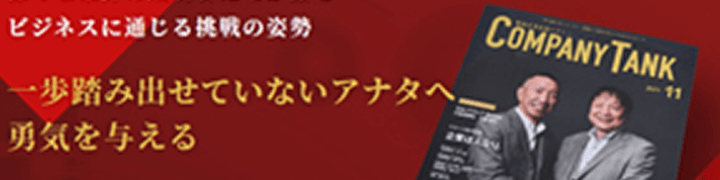コラム

キャンプやサバイバルに関するアウトドアスクールを主催しているイナウトドア合同会社の森豊雪代表が、アウトドアの魅力をお伝えする連載コラム。日本では、古くから食材や薬として用いられてきた野草。公園や道端で普段何気なく見かける野草は、食べ物として、薬草として、あるいは観察対象として、人間の生活に深い意味と価値をもたらしてくれる。今回はその野草について考察を進めたい。
◎野草の定義とその存在について
野草とは野原などに自生する植物であり、人間が意図的に栽培していない植物のことを指します。野草は、庭や道路脇、空き地、公園など、私たちの身の回りに普通に存在していますが、その一方で意外と見過ごされがちです。多くの人は野草を「雑草」として認識していますが、「『雑草』という名前の草はない」と言う方もいます。しかし実際には、野草は単なる雑草ではなく、私たちの生活にさまざまな恩恵をもたらす貴重な資源でもあるのです。
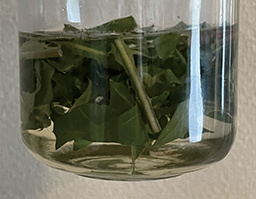 古くから日本では野草が食材や薬として用いられてきました。例えば、春の七草(セリ、ナズナ、ハコベラ、ゴギョウ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)もすべて野草の一種であり、いずれも栄養価が高く、体を健やかに保つために利用されてきました。
古くから日本では野草が食材や薬として用いられてきました。例えば、春の七草(セリ、ナズナ、ハコベラ、ゴギョウ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)もすべて野草の一種であり、いずれも栄養価が高く、体を健やかに保つために利用されてきました。
現在では「七草がゆ」のために栽培されていることもあり、完全には野草ではないとも言えますが。
◎日本の文化に根付いている野草
野草は、薬としての効果もある植物として古来より重宝されてきました。ヨモギやドクダミは、その代表的なものです。ヨモギは春になると芽吹いて、その若い葉を餅に混ぜると「草餅」になることで知られていますが、漢方薬としても用いられ、冷え性やアレルギーなどの改善に効果があるとされています。またドクダミには独特の香りがあり、苦手とする人もいますが、解毒作用があることから薬草として利用され続けてきました。これらの野草は、現在では薬膳やハーブとしての利用が進んでいます。
野草は草むしりの対象となる「雑草」として排除しがちですが、実はそれらを生活に取り入れることで心身の豊かさを享受することができるのです。例えば、都会の中でも注意深く観察すれば食べられる野草が見つかることがあります。タンポポ、スギナ、ヨモギなどは、その代表的なものです。これらの野草は、サラダやお茶、料理のアクセントとして使うことができ、食事に栄養素を加えてくれます。
 具体的には、苦みが特徴のタンポポの葉はサラダやパスタのトッピングに適していますし、根を乾燥させてお茶にすれば、コーヒーの代わりとして楽しむことも可能です。私が受講した「アースハーバリスト」講習では、これらの野草の効能や、実際に調理をして食べ方などを学びました。
具体的には、苦みが特徴のタンポポの葉はサラダやパスタのトッピングに適していますし、根を乾燥させてお茶にすれば、コーヒーの代わりとして楽しむことも可能です。私が受講した「アースハーバリスト」講習では、これらの野草の効能や、実際に調理をして食べ方などを学びました。
また、昔から漢方薬として使われているスギナはカリウムやカルシウムなどのミネラルが豊富で利尿作用もあるため、デトックス効果が期待できます。さらに、ヨモギは葉をお茶にして飲むことで、消化を助け、体の冷えを改善する効果があると言われているのです。
◎野草を採取する際の注意点
野草を生活に取り入れる際には、いくつかの注意点があります。まず、すべての野草が安全に食べられるわけではないことを認識してください。いくつかの野草には毒性があり、誤って摂取すると健康被害を引き起こす危険性があります。そのため、野草に関する知識を持つことが重要です。特に、食べられる種類と毒性のある種類を正確に区別することが求められます。もし知識が不十分な場合は、専門家に相談するか、野草に詳しい書籍を参考にするのが賢明です。
また、野草を採取する際には、その場所にも注意を払いましょう。公園や道路脇などでは、排気ガスや農薬の影響を受けている可能性があるため、なるべく汚染の少ない場所を選ぶようにしましょう。自然環境の豊かな山間部や河川敷などが理想的だと言えます。
さらに、野草の保護も大切です。採取する際には、必要以上に摘み取らないよう心がけ、自然環境への配慮を忘れないようにしましょう。万が一、サバイバルな環境に置かれ、野草しか手に入らなくなりそうになった時も同様で、その場合は、花、葉、実、茎、根など部位ごとに分けて毒性を試しながら食すという方法があります。葉が食べられたからと言って、他の部位が食べられるというわけではありません。安全な部位、すでに試したことがある調理方法でのみ食すことが肝要です。
 野草を単に食材としてだけでなく、観察対象として楽しむことも、自然と調和した暮らしを営むための1つの方法です。野草を観察することで、私たちの日常生活に自然のリズムが取り入れられ、心に癒やしを与えてくれます。
野草を単に食材としてだけでなく、観察対象として楽しむことも、自然と調和した暮らしを営むための1つの方法です。野草を観察することで、私たちの日常生活に自然のリズムが取り入れられ、心に癒やしを与えてくれます。
例えば、春になると最初に顔を出すタンポポの花や、草むらの中で小さな白い花を咲かせるハコベを見つけると、季節の変化を実感することができるはずです。夏には、青々と茂るスギナやセリが成長し、秋には紅葉が進む中で野草の実が色づいていきます。冬には一見、枯れてしまったように見える野草も、実はその根の中で次の春に備えてエネルギーを蓄えているのです。このような自然のサイクルを観察することで、私たちも自然と共生する感覚を取り戻すことができます。
◎持続可能な生活と野草の関係
野草を利用することは、持続可能な生活を実現するために有効な手段の1つとも言えます。現代の農業や食料供給は、化学肥料や農薬、輸送に大きく依存していますが、野草は自然の恵みをそのまま生かす方法です。都市化が進み、自然との距離が遠くなってしまった現代人にとって、野草の活用は自然と再びつながる機会を提供してくれます。自らの手で採取し、自分で調理することで、食べ物のありがたさを再認識し、持続可能なライフスタイルを促進することができるはずです。また、野草を活用することで、フードロスの削減や環境保全にも貢献できる点も魅力だと思います。
野草は、ただの雑草という印象から大きく離れ、私たちの生活に深い意味と価値をもたらす存在です。食べ物として、薬草として、そして観察対象として、野草を身近に感じることで、私たちは自然との調和を取り戻し、心豊かな生活を送ることができるでしょう。
次に道端や公園で野草を見かけた時には、小さな命に目を向け、その力強さと美しさに触れてみてはいかがでしょうか。

| 森 豊雪 学業修了後はエネルギー関連の製造会社に入社し、30年以上にわたって勤務する。55歳を迎えて新しい道を模索。もともと趣味で活動していたアウトドア分野で起業することを決意し、イナウトドア(同)を立ち上げた。現在は、オリジナルアウトドアグッズの開発や、サバイバル教室などの展開、自然保護のボランティア活動に注力している。 ※保有資格 ・NCAJ 認定 キャンプインストラクター ・JBS 認定 ブッシュクラフトインストラクター ・日赤救急法救急員他 ■企業情報 イナウトドア 合同会社 〒238-0114 神奈川県三浦市初声町和田3079-3 ■URL https://www.inoutdoor.work/ ■X(旧Twitter) @moritoyo1 |
 ▶イナウトドア(同)では親子向けスクールや焚き火体験なども行っております。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
▶イナウトドア(同)では親子向けスクールや焚き火体験なども行っております。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。